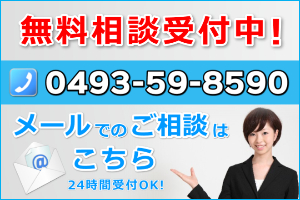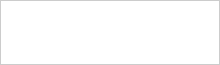相続分を侵害されるような遺贈や贈与があった場合、遺留分を有する法定相続人(兄弟姉妹には、遺留分はなし)は受遺者や受贈者に対し、遺留分減殺請求権を行使することができます。
遺留分減殺請求権の行使は、受贈者や受遺者に対する一方的な意思表示であり、裁判上でも、裁判外でも行使することができます。
もっとも、遺留分減殺請求権の行使は「相続の開始および減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年」「相続開始の時から10年」の期間内にしなければならないことになっていますから、裁判外で行使する際には、内容はもちろん、日付も証明が必要になるため、必ず内容証明郵便等を使って行うことが重要です。
遺留分減殺の対象となる贈与や遺贈が複数ある場合、まず、遺贈、次いで贈与が減殺の対象となります。
遺贈が複数ある場合には、遺留分権利者において減殺の対象となる財産を選ぶことはできず、遺贈全体の価額の割合に応じて減殺すべきことになります(ただし、遺贈者が遺言で別段の意思表示をした場合には、それに従うものとされています。)。
贈与が複数ある場合には、新しい贈与(つまり後に行われた贈与)から順に古い贈与を減殺すべきことになります。なお、複数の贈与の前後関係が分からない場合や、同時に効力を生じた場合、遺贈と同様に複数の贈与を割合で減殺すべきことになります。
なお、遺留分減殺請求がなされると、受贈者等は、対象となる財産そのものを返還しなければならないのが原則です。
ただし、現物を返すのが困難な場合もありますから、民法では、受贈者等は、減殺を受けるべき限度で価額を弁償して現物返還を免れることができるものとされています。
遺留分減殺請求通知書の見本
遺留分減殺請求通知書
私は、被相続人田中○郎の法定相続人として、貴殿に対し、下記のとおり通知します。
記
被相続人は、平成○年×月×日付遺言公正証書により、貴殿に対し、不動産、預貯金その他一切の財産全部を相続させる旨の遺言をなし、平成○年○月×日、死亡しました。
これにより、私の遺留分が侵害されています。
よって、本書をもって、遺留分減殺請求を行使いたします。
平成○年○月○日
住 所 埼玉県坂戸市・・・
相続人 田 中 ○ 美 印
司法書士による無料相談受付中!
司法書士田中事務所では、相続登記(土地建物の名義変更)、遺言書作成、相続放棄、成年後見、生前贈与、財産分与、抵当権抹消などの手続に関する無料相談を行っています。
ご相談はお電話はもちろん、専用フォームからも24時間受け付けております。
土日・夜間のご相談も可能です。